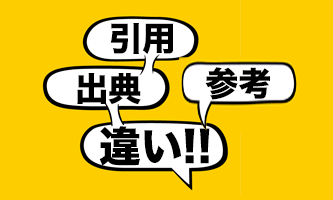ブログなどでインターネット上に投稿する記事を書くときに、「引用」「参考」「出典」のどの言葉をどのように使えば良いのか迷う人は少なくありません。
このページでは「引用」「参考」「出典」の違いと書き方のルール(著作権)をまとめています。
「引用」「参考」「出典」の言葉の意味の違い
「引用」「参考」「出典」の違いは明確です。
「引用」と「参考」が他の著作物にある文章や画像の一部を引いてくる行為であるのに対して「出典」は文章や画像を引いて来た著作物そのもののことを意味します。
「引用」「参考」「出典」の違いをまとめると次の通りです。
【参考】もとの著作物などの内容を要約して使うこと
【出典】引用または参考にした著作物そのもののこと
【著作権】「引用」「参考」の正しいルール
「引用」「参考」「出典」の言葉の違いはいたってシンプルですが、「引用」や「参考」を自分の記事の中に入れるのにはルールがあります。
ルールとは著作権のこと。この言葉をあなたも一度ならず耳にしたことがあると思います。正しく理解すべきはこの一点。知らなかったでは済まされません。
あなたは今、自分のブログやサイトに記事を投稿しようと考えているはずです。
たとえ自分だけの日記のつもりで書いているブログであったとしても、それがインターネット上にある限り、それはあなた以外の誰もが簡単に読む・見ることができます。
日記といえども誰もがそれを読む・見る環境下にある限り、ルールを守る必要があります。以下にそのルールをまとめてみました。
【著作権】で定める「引用」とは
そもそも著作権法では「引用」のルールをどのように定めているのでしょうか。以下に引用した箇所が著作権法で定められた「引用」です。
【引用】
著作権法第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
出典:著作権法第32条
著作権法第32条では「公正な慣行に合致する」「正当な範囲内」という条件さえクリアすれば「引用」はしてもよいとしています。
では「引用」しても良いとされる条件「公正な慣行に合致する」「正当な範囲内」とは具体的にどのようなことでしょうか。
最も一般的に言われているルールは以下の6つです。
- 引用する必然性がある
- 質量ともに、自分の文章が「主」で引用は「従」
- 自分の書いた部分と引用部分をはっきりと区別する
- どこから引用してきたのかを明記する
- 未公開の著作物からの引用はしない
【1】引用する必然性がある
評論する目的があったり自分の主張の裏付けとして使うなど、引用しなければどうしてもあなたの文章が成り立たない場合、引用が可能です。
ただし引用を正当化するために、わずかばかり論評やレビューを入れておくようなネットの記事をよく見かけますが、この場合は引用の必然性は認められません。
そもそも引用すること自体が目的になっていますからね。
![]()
【2】質量ともに、自分の文章が「主」で引用は「従」
あなたの書いた文章があくまでも「主=メイン」でなければなりません。あなたの書いた文章に対して引用した箇所は「従」であることがはっきりわからなければなりません。
この「主」と「従」の関係を文字量だけで解釈する人もいますが、質においてもあなたの書いた文章が「主」である必要があります。
ここで言う「質」とは、引用した文豪の文章を超えるものをあなたが書かなければならないと言う意味でありません。
文豪の文章を引用したあなたのオリジナル文章が読み手にとってどれほどの価値があるものなのか。その点が重要です。
よって、たとえあなたの書いた文章の方が引用箇所よりどれほど長かったとしても、オリジナル文章が適当に書かれた無価値なものである限り「主」と「従」の関係は成り立たないと考えるのが無難です。
![]()
【3】自分の書いた部分と引用部分をはっきりと区別する
あなたの書いた文章の中に、他人の著作物などをあたかも自分が書いたかのように忍び込ませてはいけません。
あなたの書いた文章と引用した箇所とが誰の目にもはっきりと区別がつくように表示しなければなりません。
印刷物などではカギカッコなどを使えば事足りますが、ブログの場合は「blockquote」というタグを使って引用箇所を表示するのがオススメです。
![]()
【4】どこから引用してきたのかを明記する
あなたが自分のブログの中に他の著作物からの引用を行なった場合、その出所を引用箇所のすぐ近くに明記しなければなりません。「出典」を明記するということです。
本からの引用であればその本のタイトルや著者名・翻訳者名。他のサイトからの引用の場合であればそのサイト名やURL、リンクを貼ればさらに丁寧な出典の表示方法と言えます。
![]()
【5】未公開の著作物からの引用はしない
作者が身内だけに公開したような著作物、まだその著書が発売日を迎えていない場合の著作物などの引用はできません。
すでに公開(発売)されている著作物に限って引用が可能です。
【6】引用した箇所の改変を行なってはならない
引用した箇所をあなたの都合で勝手に変えてはいけません。
ただし引用箇所が長すぎになるのを避けたい場合であれば(中略)などという文言を添えて一部を省略していることを読者にわかるようにすれば問題はありません。
また、原文に明らかな誤植がある場合でもそのまま引用して(原文ママ)という文言を添えて原文のあるがままに引用していることを伝えるようにしましょう。
![]()
【著作権】誤解だらけの「参考」
もとの著作物をそのままの形で安易に引用する行為はやってはいけないこと、というのはよく知られていることですが、誤解が多いのが「参考」です。
上に述べた通り「参考」とはもとの著作物を自分なりに要約して、自分の文章に埋め込むことです。
しかし、ネット上などでは「です、ます」調を「である」調に書き換えただけ。原文にある単語を類義語に置き換えたものも少なくありません。
ここまでやってしまうとそれは「要約」とは呼べません。
「引用」でなく「参考」として他の著作物のコンテンツを引いてくる場合でも、「引用」のルールに沿って「参考」を掲載するようにしましょう。
「引用」「出典」「参考」の違いと使い分け、書き方のルール
最後にもう一度、「引用」「出典」「参考」の違い。そして「引用」の正しい書き方のルールを以下にまとめます。このページの情報があなたのお役に立つことができれば幸いです。
【参考】もとの著作物などの内容を要約して使うこと
【出典】引用または参考にした著作物そのもののこと
- 引用する必然性がある
- 質量ともに、自分の文章が「主」で引用は「従」
- 自分の書いた部分と引用部分をはっきりと区別する
- どこから引用してきたのかを明記する
- 未公開の著作物からの引用はしない