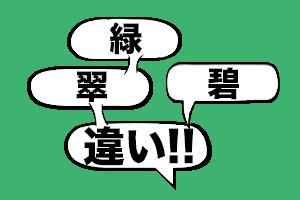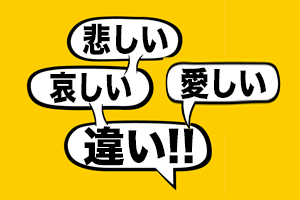「青」「蒼」「碧」。どれも「あお」と読み英語でいう「ブルー」の色を指す言葉と思われていますが、「蒼」「碧」は実際には「グリーン」に近い色です。
「青」「蒼」「碧」、三つの「あお」の色の違いは次の通りです。

このページでは、「青」「蒼」「碧」、三つの「あお」の色の違いだけでなく意味の違いについても詳しく解説しています。
【青、蒼、碧】三つの「あお」の色と意味の違い
【青】
「青」と聞いて真っ先に思い浮かべるのは、晴れ渡った日の昼間の青空の「青」。真夏の炎天下の中の「青」い海。
しかし「青」は、本来は白や黒、そして草木の緑まで範囲の広い色を指す言葉として使われていました。
現代もでつややかな黒毛の馬のことを「青毛の馬」。信号機の「ススメ」のシグナルの色がグリーンであるにも関わらず「青」と呼ぶのは、「青」という言葉の古い使い方の名残りと言われています。
なお、現代の「青」は英語でいうブルー系統の色の総称として最も一般的に使われ、また「青」「蒼」「碧」の三つの「あお」の中では唯一の常用漢字です。
「ブルー」系統の色を書き表す場合には「青」を使っていれば間違いありません。
【蒼】
「蒼」は、草木が茂るさまを表す言葉で、草木が生い茂っていることを意味する「鬱蒼」に「蒼」という漢字が含まれています。
そのため、日本の伝統色の「蒼色」はブルーではなくグリーンです。
ところで「蒼」という言葉は、もともとは目立たない色を表し、そこには灰色も含まれていました。
顔面蒼白、蒼白い顔などという時の「蒼」は、ブルーというよりは、目立たない色や灰色など寒々とした色を意味するとも言われています。
また、天候の悪い日の寒々とした海の様子を「蒼い海」などと表現しますが、これも目立たない色や灰色の名残ではないでしょうか。
ただし最近では、快晴の日の空を「蒼天」「蒼空」などと呼び、「青空」と同様の使われ方をされるケースが少なくありません。
【碧】
大半の国語辞典では「碧」を「あおみどり色」と解説しています。
ブルーと比べるとグリーンに見え、グリーンと比べるとブルーに見えるのが「碧」で、実際に「碧」という漢字は「みどり」「あお」という訓読みを持っています。
「碧」は色の表す言葉であると同時に「碧玉」の意味も持っています。
「碧玉」とは石英の結晶で、縄文時代の祭祀などに使われた勾玉の素材が「碧玉」です。
「碧玉」の色は一定ではなく、ブルーに見える「碧玉」、グリーンに見える「碧玉」、ブルーにもグリーンにも見える「碧玉」など様々な色があります。
【青、蒼、碧】三つの「あお」の違い、まとめ

「青」「蒼」「碧」、三つの「あお」の違いはこのページの解説でおわかりいただけましたでしょうか。
「蒼」と「碧」は、これらの言葉の受け取り方によって誤解を生じかねません。必要がない限り「青」を使うのが無難な使い分けと言えそうです。
- 【青】ブルーの総称で常用漢字
- 【蒼】伝統色はグリーンに近い
- 【碧】グリーンに見えるブルー