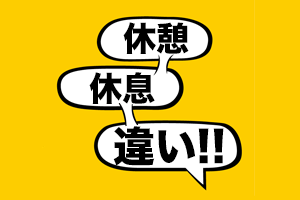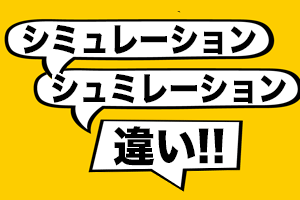「飢饉」と「飢餓」はともに、食糧が不足して飢え苦しむことを意味する言葉ですが、両者の違いは次の一点にあります。
- 【飢饉】一時的・地域的な食糧不足
- 【飢餓】永続的・慢性的な食糧不足
このページでは「飢餓」と「飢饉」の意味の違いと使い分け方についてさらに詳しく解説しています。
【飢饉・飢餓】意味の違いと使い分け
【飢饉(ききん)】一時的・地域的な食糧不足
飢饉(ききん)とは、凶作などによって食物が欠乏し多くの人々が飢えに苦しむ現象を意味します。
飢饉(ききん)をもたらす凶作。その凶作の主な原因には、次のような事象が挙げられます。
- 干魃による水不足。
- 台風などによる洪水。
- 異常気象による冷害。
- 害虫の繁殖。
- 火山の噴火や大地震などの天災。
これらの事象の多くは一時的・地域的なものです。そのため飢饉(ききん)は、自ずと一時的・地域的なものになるという特徴を持っています。
【飢餓(きが)】永続的・慢性的な食糧不足
一時的・地域的な飢饉(ききん)に対して、飢餓(きが)は永続的・慢性的に、食物が欠乏し多くの人々が飢えに苦しむ現象です。
永続的・慢性的な食糧不足を引き起こす主な原因には、次のような事柄が挙げられます。
- 農業行政の失策や破綻。
- 流通の不備や不具合。
- 長期にわたる戦争による減産。
また、政治的な無策などによる貧困層の増大、食物の価格の高騰などにより、食糧不足でないにもかかわらず、多くの人が飢えに苦しむ場合も少なくありません。
このような人為的に発生した現象も飢餓(きが)の一部です。
【参考】「飢饉」と「飢餓」の意味
「飢饉」と「飢餓」。それぞれの言葉の意味は次の通りです。以下は『広辞苑』より引用しています。
【飢饉】
農作物がみのらず、食物が欠乏し、飢え苦しむこと。食物以外でも必要な物資がいちじるしく不足する場合にいう。
【飢餓】
うえること。うえ。一時的・地域的現象である飢饉と対比して、永続的・慢性的な食糧不足や低栄養状態にいう場合もある。
出典:岩波書店『広辞苑』
【飢饉・飢餓】意味の違い、まとめ
「飢饉」と「飢餓」の意味の違いと使い分け方を区別するポイント。このページの解説でおわかりいただけましたでしょうか。
最後にもう一度、このページで述べた「飢餓」と「飢饉」の意味の違いを区別するポイントを以下にまとめます。
| 飢饉 | 飢餓 | |
| 主な特徴 | 一時的 | 永続的 |
| 主な原因 | 凶作 | 行政の無策 |